 | 第10章 |
2004年1月 有羽 作 |
|
お互いの熱を奪いあうように夢中で抱き合ったけれど、正直大変だった。 服は濡れたまま身体に張り付いていて、脱ぐのも脱がすのも容易ではなかったし、真珠(まじゅ)の身体を気遣うとおのずと俺は無理な体勢で、おまけにゴツゴツとした桜の幹で背中や腕をいささか擦り剥いた。 嵐が通り抜けたあとのような、静かな時間の中でしばらく抱き合っていた。 服の乱れを整えると、真珠(まじゅ)は呟くように言った。 「変なお願いして、ごめんね。でもね、私がこの世から消えてしまっても、きっと今夜のことをあなたは思いだすわ。そのうちすぐに、あなたは私のぬくもりや私の顔さえも思いだせなくなる。そして別の女の子に恋をするの。でもね、秋の夜中に公園に忍びこんで、ボートにふたりで乗って池に落ちた事や、桜の大木の下で夢中で愛し合ったことは、きっと思いだすわ。ねえ、そうでしょう?」 そう言うと、再び俺に近づき胸に顔をうずめた。 そのまま微動だにしない彼女の身体を抱きしめていた。 なんだか、胸のあたりが暖かく…濡れているような気がして、真珠(まじゅ)の顔を覗きこんだ。 真珠(まじゅ)の頬は濡れていた。 彼女は声もたてずに俺の胸で静かに泣いていた。 それが最初で最後に見た、真珠(まじゅ)の涙だった。 そして、その涙を見て俺は、真珠(まじゅ)の今夜の馬鹿げた行動の全ての意味を理解したんだ。 真珠(まじゅ)の切ない思いが俺に押し寄せてきて、なんて言葉にしたらよいのか分からなかった。 「君がいなくなっても、君はずうっと俺の中で生き続けるよ。俺が別の誰かに恋しても、きっとそれは変わらないって断言できる。忘れるなんて絶対にありえない。」 そう言ったが、嘘をついた訳ではないのに、やっぱり言葉にすると嘘くさい気がしてちょっとだけ自分が嫌になった。 「ありがとう。もうあなたに我がまま言ったりしないから…。ごめんね。」 その夜以来、彼女が俺に無理を言うことは無かった。 でも逆に俺は淋しかった。 少しずつ見えない何かが、ふたりを引き離しているように思えていたのは俺一人だけだったのだろうか。 逃れようも無い“さよなら”の気配に俺は怯えていたんだ。 でも君の意識はもっと別のところにあって、そんな俺をいつも優しく包んでいた。 いつのまにかふたりの立場は逆転していた。 俺を不安にさせないように、君は少しずつ強くなっていった。 馬鹿げたことばかりして、秀明を呆れさせたかもしれない。 私は自分自身を時々コントロールできなくなるところがあったけれど、でも…今夜を最後に彼を困らせる事だけはやめにしようと思った。 池に落ちてビショビショになった身体で抱き合ったけれど、秋の冷たい風は急速に私達の熱を奪った。 その晩、彼は私の部屋に泊まった。 横で眠っている彼の裸の背中には、痛々しい傷があった。 きっと、公園の桜の幹に身体を押しつけていた時に擦り剥いたんだろう。 ‘ごめんね’口には出さずに呟いて、その傷をそっと指でなぞった。 彼はぐっすり眠っているようで、全然、目を覚まさなかった。 今夜のことで私の中でずうっと迷っていたことの答えが出ていた。 私は、ベッドを抜け出すとドレッサーの引きだしの中から、鋏を取りだした。 そして、私の足はその鋏を掴むとバスルームへと向かっていた。 バスルームの鏡の前に私は立っていた。 13歳の時からずうっと伸ばし続けていた髪は、いつも胸の上より短く切ったことがなかった。 役柄上、短くしようかと思ってはいたけれど、様々な思いが私の決断を揺るがしていたんだ。 でも、もういい。もう迷いはなにも無くなっていた。 ‘ジョキッ、ジョキッ’ という音と共に一筋の髪の毛が床に落ちた。 「真珠(まじゅ)、なにやってんだ!」 目を覚ました秀明はバスルームに入ってくると、驚いた顔をして私の鋏を持っている方の手首を掴んだ。 「なんのつもりでこんなことするんだよ!」 ちょっと怒った顔で彼は私を睨んでいた。 「今度の役はこのほうが演じ易いかな…と思って。別に驚くようなことじゃないわ。」 彼は狐につままれたような顔をしていた。 「でも…いいの? 長い髪似あっているし、ほら、女の子にとって髪の毛って大切なものだって言うじゃない。」 「うん、いいんだ。それに今度の舞台を最後に、芝居はもうやめようって決めたの。だからまあ、ある意味、失恋みたいなものだから…。」 私はそう自分に言い聞かせるように言った。 「やめるって…それで、本当にいいの?」 「うん。体力的にも限界かもしれないし、母がね…もうやめて戻ってきてくれって泣くの。それに、私には芝居よりも大切なものが分かったし。…今夜のことで、私にとって一番大切なのは…秀明なんだって気が付いたから。私の時間はきっと、死から盗んでいる時間だから、もうあとはあなたの事だけを考えていたいの。だから、芝居はもうこれで終わり。髪を切るのは役作りを兼ねた、いわば、決意表明みたいなものなんだ。」 「そんなこと考えていたんだ。じゃあ、もう今度の舞台が最後なんだね。」 私よりも、彼の方が淋しそうに見えた。 「ねえ、髪の毛切ってみない? 断髪式だから、あなたも鋏をいれてくれれば嬉しいな。」 そう私が言うと、秀明は複雑な表情をして私から鋏を受け取った。 そして、私の髪の一筋を手に取ると、一瞬戸惑ったが息を呑み、それを鋏で顎のあたりの長さに切った。 それから、鋏の音がしばらくバスルームに響いた。 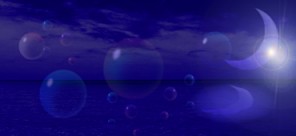 鏡の中には今まで見たことも無い女の子が立っていた。 こんな事くらい全然平気だと思っていた。 でも、どうしてだろう…言葉では説明しきれないような切ない気持ちになった。 「大丈夫?」 彼は心配そうな顔をして、鏡の中の私を見つめた。 「なんだか、凄く不格好で笑える…昼間、美容院でもう一度切ってもらわなきゃ。」 私は無理にそう言って、笑った。 「馬鹿だな…泣きたいなら泣けばいいのに。俺の前では無理する事ないよ。」 秀明はそれ以上は何も言わなかった。 それが彼の優しさだってことも分かっていた。 でも、私はここで泣くわけにはいかないんだ。 もしも今ここで泣いたら、きっとまた我がままで自分勝手な私に戻ってしまうような気がした。 バスルームから出ると、もう窓の外は夜明けの光りが射し始めていた。 「ほとんど眠れないうちに、朝になっちゃた。ごめんね。」 「今日の真珠(まじゅ)は謝ってばかりいるね。俺はひとつも迷惑に思ったことなんてないよ。それよりも、君が何を考えているのか分かったから…いつも、君の考えていることの半分も俺は分かっているのかな?って自信がなかったから、嬉しかった。」 彼はそう言ってくれた。 私達はその日、時間が許す限り一緒にいた。 そしていろんな事…とりわけもうこれで最後だという思いからか、芝居のことについて彼と話した。 「私ね、最近になって自分がどういう俳優になりたかったのか、やっと分かったんだ。ねえ、みんなどうして映画館や劇場に足を運ぶか分かる? それはね…自分以外の人間が一体どんなことで悩んでいるんだろうって気になっているからなの。だから、大勢の人間が映画館や劇場に足を運ぶのは、そのことを探りだすためなんだと思う。そして、観客は暗がりの中にいて、スクリーンや舞台上の人物になったように感じるの。それは凄く単純だけれど、とても複雑なことだから魅力的なんだよね。私はそんな観客に共感して貰える俳優になりたかったの。」 「そこまで分かっているなんてうらやましいよ。俺にはまだまだそこまで、自分のことがみえていない。ただ、漫然と一生懸命に演じるだけじゃ、能が無いってことだけは分かっているけど…。」 「前に秀明は世間の評価が全てじゃない…って言ったよね。私はその言葉に感動したんだ。あなたはきっといつか、素晴らしい俳優になれる日が来る。いるだけでまわりを幸せにできる空気を持っているんだし、有名になって、ただ上手いと言われる俳優で終わって欲しくないの。見ている人に共感して貰える魅力的な俳優になって貰いたいの。私が果たせなかった分も…。」 そこまで言って、また少し淋しくなっていた。 「ねえ、劇場やスタジオには“お芝居の神様”がいるんだよ。」 「ああ…分かる。なんとなく俺にも見えるときがあるよ。」 「自分の意識と別のところで凄くいい芝居ができたりすると、“今日はお芝居の神様がいた”って思えるんだ。私が死んだら、私はお芝居の神様の弟子になるの。」 「じゃあ、俺が芝居をしている時は、どこからか真珠(まじゅ)が見ているってことだね。」 「そうだよ。いつも見ているんだから。」 私はそう答えて笑ったが、彼は淋しそうな顔をした。 私の幕は、まだ降りてはいない。 今は、出きる限りのことをしよう。 そして、舞台の幕が降りたとき…彼のことだけを考えるんだ。 神さまが私に与えてくださった、最後の恋は…あの晩、西の空に輝いていた三日月が運んできたんだ。 そしてふたりの恋は、私がいなくなることで、もうすぐエピローグを迎えようとしているかにみえた。 でもそれは物質的な最後を意味しているだけで、私にはもっと大切なことが見え始めていた。 「君はずうっと、俺の中で生き続ける…」 そう言った彼の言葉を信じようと思った。 だってあの夜から、とても穏やかな気持ちで、彼と向かい合うことができたんだ。 |
|
つづく
|